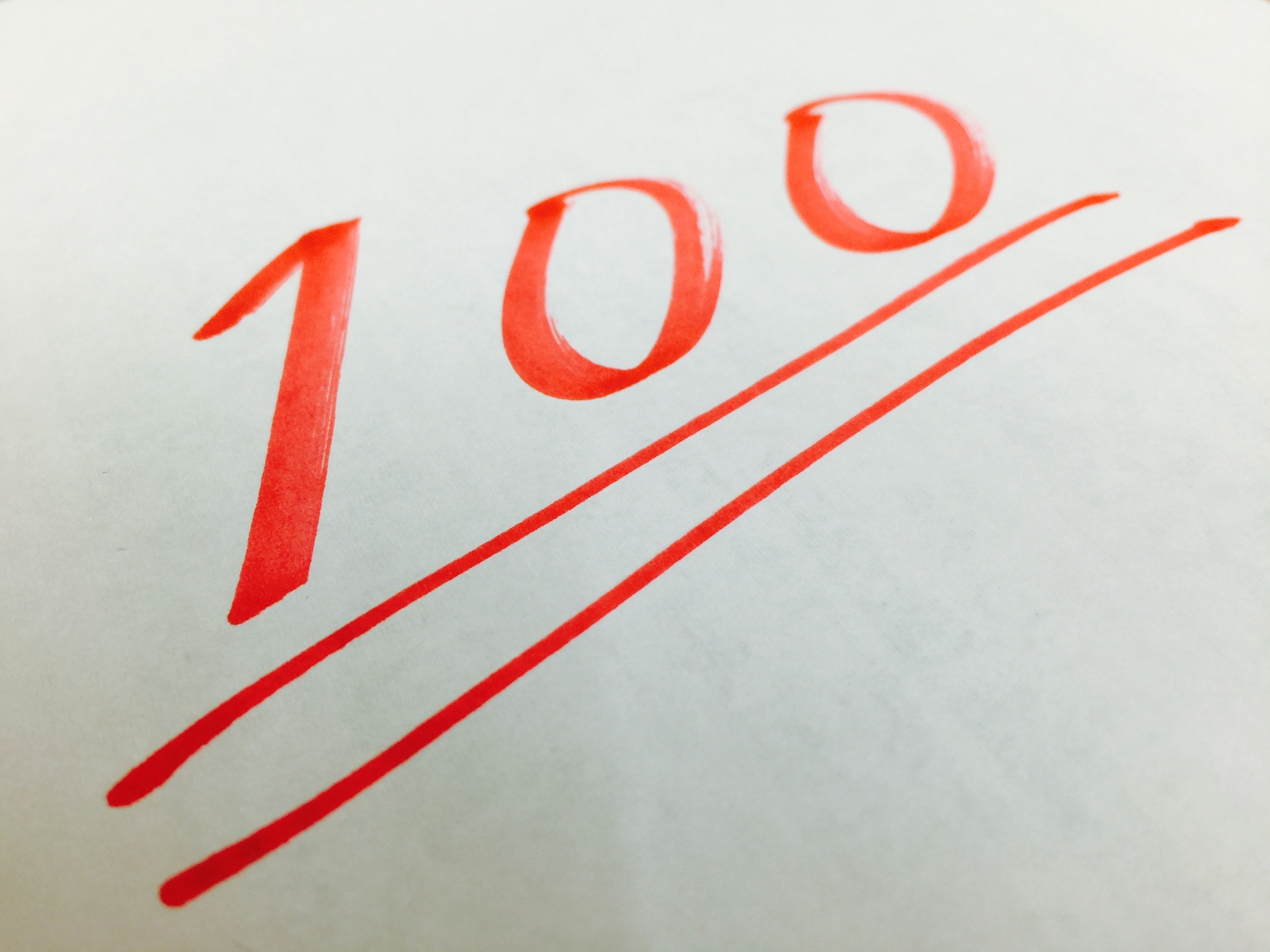【塾長ブログ】夏に備えて模様替え

塾長の新井です。今日は、「夏に備えて模様替え」というお話をさせていただきたいと思います。
タイトルを読んで字の通りですが、昨晩、貴志コーチと教室の模様替えを行いました。というのも、星学院では自習スペースを提供しているのですが、夏休みを目前に控え、利用を希望するホシガク生が増えてきたからです。
新レイアウトは写真の通りです。前のレイアウトをご存知の方からするとかなり変わった印象を受けられるのではないでしょうか。
ちなみに、このようなレイアウトにするのには理由があります。
1)学習の様子をコーチが見ることができる
2)机の前にスペースを確保する
1つ目に関しては、担当コーチが(学習の)進捗をしっかりと見られるようにすることで、効率的な学習を実現したいという狙いがあります。また、自習していると分からない問題で手が止まってしまうケースが多くありますが、常にコーチが見られるようにすることで、このような問題でのロスタイムを減らせると考えています。
次に2つ目に関して、机の前に壁があると圧迫感が集中の阻害要因になってしまうということで、全ての席において机前のスペースを確保した次第です。ちなみに、これはご自宅の勉強部屋のレイアウトなどを決められる際も参考になるのではないでしょうか。
さて、新レイアウトでの授業は今日からスタートです。
自習スペースを利用したいと考えている皆さん!ぜひ貴志・新井いずれかのコーチにご相談ください!! 一緒に大きく飛躍する自習プログラムを考えましょう^^